
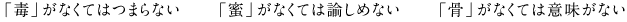
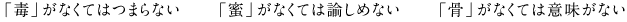
職業作家ではなくとも、何かを書いてみたいという人は存外多いのではないだろうか。
私にも、長年、書きたいもの、書きかけのものが数多くある。
「それ、書かせてよ」
今からおよそ十九年ほど前、私は、近しい知り合いの女性にそう言ったことがある。
しかし「きっといつか書くから」と言ったそのときの約束は、いまだに守られず一文字も書くことができないでいる。当時二十七歳だった彼女は、すでに四十六歳になった。
その女性の祖父は、清木美徳(せいきよしのり)といった。
長崎大学(長崎医科大学附属薬学専門部)の物理学教授(理学博士)で、その後、広島大学の教授を経て退職し一九九九年に他界している。話を聞いたのは亡くなった一年後ぐらいのことだった。
八十歳を超えたある日、清木氏は、いきなり「日本史を勉強する」と言い出した。
なぜなのかは誰にも分からない。その日から書斎に閉じこもりひたすら日本史を研究した。どこに何かを発表するでも、だれかに話をするでもない。十五年間学び続け、九十五歳で亡くなった。そして「まだ日本史の勉強が終わらない」と言い遺したそうである。
彼女の祖父はいったい何を学んでいたのか。物理学専門の清木氏に何が起こったのか。
彼女の記憶に残っているのは、臨済宗の名僧、白隠禅師の「南無地獄大菩薩」という言葉を、祖父がよく色紙に墨書きしていた姿だった。まだ幼かった彼女には、その意味はよく伝わらなかった。
ちなみに「南無地獄大菩薩」というのは、地獄への畏(おそ)れが、人々の菩提心を醸成する、という意味らしい。
一九四五年(昭和二十年)八月九日、長崎市に原子爆弾が投下された。
B-29グレート・アーティストを操縦したチャールズ・スウィーニー少佐は、ポール・ティベッツ大佐から、第一目標は、福岡県小倉市で、第二目標が長崎市であることを告げられたという。
先に飛んだエノラ・ゲイからは、小倉市には朝靄がかかっているが快晴が期待できるとの報告があり、ラッギン・ドラゴンからは、長崎市は曇っているが、雲量は十分の二である、などの報告があったとされている。のちの研究で、この雲の正体についてはかなり分析されている。
九時四十四分には、原爆の投下目標である小倉陸軍造兵廠上空へ到達したものの、当日の小倉上空を漂っていた霞により投下目標確認に三回失敗。それで第二目標の長崎に、原爆「ファットマン」が投下された。わずかに雲の間から目標が見えた、その一瞬が原爆投下を成功に導いた。
私の生まれ育った北九州市では、小学校のころから、「本当は、この原子爆弾は北九州に落とされるはずやったけど、天気が悪くて長崎に落とされたんよね。私らは長崎の人に足を向けて寝られんね」と教師から教わった。「長崎にお詫びせにゃ」と言われてきた。
子供ながらに、「もし長崎やなくて小倉に落ちたらオレらは生まれてこんやったやん」と話した記憶がある。そういう地元で教えられる小倉から長崎への原爆投下の変更状況は、全国の常識だと思っていたが、そうでもないらしい。
清木家もまた偶然に、原爆被害から免れた。清木美徳氏の妻が七番目の子を身ごもったが流産したのは、原爆の落ちる数日前だった。そのために疎開先から長崎に皆が戻ることを断念していた。もし戻っていれば生き残ったのは清木氏だけだったかもしれない。
その一九四五年八月九日の朝。清木氏は、長崎大学の学生らとともに研究所の近くで防空壕を掘っていた。
この防空壕堀りというのは、薬専校舎正面の丘の裾に、清木氏の設計指導で掘り始めたものだった。物理学者の設計らしく爆風の入るのを避けるために、まず防空壕の正面に狭く深い三メートル余りの排水路兼用の溝を作る。その溝の低部側面から丘の中心に向かって数本の壕が延びる特殊な形なので、かなりの難工事だった。壕中で、つるはしや鍬をふるって掘る班と壕の外で土を運ぶ班に分かれ、時間交代ですすめられた。
校庭に隣接した射撃場の溝から、さらに東南の丘をめがけてえぐり抜かれ、当時、奥行十メートル、高さにして、一・五メートルの円形壕は、入口を二つにして、丘の中で会合する相当に頑強なものになっていたことが記録されていた。
真夏の暑さのなか、上半身裸で作業する学生も多かった。
壕掘り作業に集まったのは、三年生二十九名、二年生九名。
午前十一時ごろ、清木氏が壕内での掘削を進めていたときに、原子爆弾が落とされた。現在の平和公園や爆心地公園の東、すなわち爆心地から約七百メートルの地点にこの防空壕はあった。
かすかなB29の金属音が響く。
「あの音!! 静かに」
雷鳴と地鳴り、猛烈な激震。
防空壕内にいる清木氏と5人の学生には、何が起こっているかはわからない。
呼吸は苦しく、数十秒の間なにも覚えず。
「壕の入口にB29が落ちたらしい。入口がふさがったぞ。おれたちは生き埋めにあったぞ」
「おい大丈夫か、傷はないか、くわをとって入口を掘り出さねばならん。ぐずぐずしては生き埋めだ」
防空壕の入り口から光が差し込み、どこからか、冷たい空気が流れてくる。
「先生! われわれは助かりました。どこかに出口が開いているに違いありません」
ところが、その入り口から生徒が外を見て叫ぶ。
「先生! 外は大変です。建物もなにもありません。早く、早く!」
長崎大学薬学部百年史にある「原子爆弾による被災」の『忘れ得ぬ日』(冨田恒夫氏/武庫川女子大学名誉教授)によれば、清木氏とともに防空壕にいた学生だった冨田氏は、当時のことを次のように記していた。
そこに、入口から真っ黒の人影が飛び込んできた。
私は両手で抱きあげ、顔を見た時ぞっとした。これが人間、否、動物の顔だろうか。全身の皮膚はぬるりとして血がにじみ、頭髪も眉毛も焼け落ち、顔面は焼けただれ、正しく埴輪の形相で、この世の姿とどうしていえよう。
「君はだれか」
私は失礼とは思ったが、聞かざるを得なかった。
「松本登だ」
ああ、かの美青年を、今にしてだれが想像し得よう。
私は肩につかまらせて、壕の奥へ横たえてやった。
「おれは残念じゃ。B29一機から三個の色のついた落下傘を見た時、ちょっと普通の落下傘とようすが違うがと思い、もしか広島に落ちたものと同じじゃないかと、とっさに想像して入口まで逃げたんじゃが、もう一度見上げた時、アツという間にたたきつけられた。痛い。なんとかしてくれ」
彼の意識ははっきりしていたが興奮は非常なものだった。
その間に清木先生や椎名が、大やけどの友を壕へ運ぶ。私は壕の中へ順々に導いては横にさせてやったが、一人一人、名前を聞かねば見さかいがつかない状態であった。
「君はだれな」
「池田だ。冨田ッ、わいはぜんぜんけがしとらんね。おいの姿はどげんな。まぶたが焼けついて、眼がよう開かんが………」
ああ、なんということか。
無傷の自分を見なおした時、私はみなに相すまぬと思った。一応だましてはみたが、なんの薬にもならない。
僚友はみんな、両手を前にあげて、手首からただれた薄皮をダラリとさげたまま、やけどの苦痛を耐えしのんでいた。私の顔を見上げている姿に接しては、じっとしておれず、先生や椎名等とみんなを励まして回るだけだった。
荒木は真正面からペニスをやられ、その苦悩の姿は見るに耐えない。
宮本はすでに食道を犯されいるごとく、「富田、おれの下宿に行って征露丸をとってきてくれ」と泣き叫ぶ。
約十二、三人の友を壕内に引き入れた。この間にも壕の外では、十一人の僚友が池田、椎名の後をたどって、穴弘法の山はださして登って行ったというが、全身の苦痛と熱線傷のために、ことごとく中途で悲惨な最後を遂げたと思われる。
「永井さん」
「おお、清木先生ですか。あなたも無事でなにかでしたなあ」
固い握手がかわされた。
「いや、薬専の学生を壕に残している。私はどうでもいい。だれか学生たちを助けてくださらんか」
手を合わせて哀願された。
しかし見渡すところ、元気な教授も、助教授もいなかった。
この『忘れ得ぬ日』の記述を読んだ彼女、すなわち私の知り合いの清木氏の孫娘は、祖父が被曝したことは知っていても、このような状況にあったとは知らず、衝撃を受けた。
そしてまた私も、『長崎の鐘』や『この子を残して』という名作を遺した著名な、医学博士の永井隆氏のことは聞いたことがあっても、永井氏とともに爆心地にいたという、この清木美徳氏については知らなかった。なぜなのか。
永井氏は、自らが被爆しながら多くの被爆者を治療、救済した人物として知られている。一九五一年に長崎医大で逝去した永井氏は、四年半で十七冊の著書を残した。その作家活動はすさまじい。
被曝する二か月前には、慢性骨髄性白血病にかかり「余命三年」の宣告を受けていたというから、死までの数年間を、そのことに費やしたのは黒澤明監督による映画『生きる!』を思い出させた。
永井氏の書いた『長崎の鐘』は、GHQの検閲もあって出版するにも壁があった。初めて出版される被曝の書であり、その内容は凄まじい。アメリカとしてもかなり都合が悪かったのだろう。日本軍の侵略犯罪である「マニラ虐殺」と合本しなければ出版させないという。出版許可までに二年半の年月が費やされた。
永井氏と対照的なのがこの清木氏である。
その現場にいながら、清木氏は、その後の人生を永井氏のように、そういうふうには生きなかった、ということであろう。そこが私の最も関心のあることだった。
夏休みなどに孫娘が、祖父の家を訪ねたときには、家族全員が、毎朝八時半から三十分間、抹茶を飲みながら祖父からの説教や講義を聞く時間が設けられていたという。祖父とともに全員が般若心経を唱えねばならない。しかしそういう祖父との時間においても、彼女は「原爆に対して反対する」というような言葉を聞いたことがなかった。彼女いわく、そういう思想や運動に対しての拒否感もあったらしい。
清木美徳氏には、六人の娘がいた。結婚して子をもうけ、さらに孫ができ、相応に成功し幸せな人生を送っている。
例えば、清木氏の長女は、陸軍士官学校卒業後、九大を出た人に嫁ぎ、もう一人の娘も軍の師範に嫁いだという。あるいは産婦人科医のところに嫁に行った薬剤師、高校英語教師になった者もいた。そして私の知り合いであるその女性の母もまた、大学院を卒業し化学系の上場企業に勤務する男性と結婚している。さらに娘の一人は、自身が内科小児科医になっている。
私が当時、「書きたい」と思ったのは、同時に「知りたい」という欲求が芽生えたからだった。
極めて保守的な家系。そのなかで、他界してなお威厳を持ち続ける清木美徳氏。親類縁者が毎年のように集まり、この美徳翁を崇め親しみ、みなが当時の話題に花を咲かせる。
相応に人生を全うした人々のなかで、だれひとり超えられない語り継がれていく人物。それが清木美徳氏なのである。
それが昭和初期からの封建制度、家制度の名残であるといえば、それはそうであろう。また理系一家における学歴依存、特に医師の世界においての、といえば、それも間違いのないことに思える。
内科医になった清木氏の娘の一人は、江見順子氏といい、アメリカのニューヨーク日系人会ではかなり著名な人物である。ブロンクスのリヴァデールで小児科内科専門医として開業し四十年以上にわたりニューヨーク近郊の日本人の医療に貢献した。
調べてみると江見氏は長崎大学の医学部に入学したのちに、九州大学医学部に編入。そしてフルブライト奨学生としてウイスコン州病院でインターンシップをしている。
いまのように誰でも海外に行ける時代ではないだけに、行く方も行かせるほうも相当な決心と力が求められたに違いない。
さらに、一九六〇年には、ニューヨークに移りアルバート・アインシュタイン医科大学のモンテフィオーレ病院の精神神経内科でレジデント。その後、国立衛生研究所の研究員となり、ロードアイランドのニューポートで軍医をしていた江見啓司氏と出会い、一九六一年に結婚していた。江見啓司氏はニューヨーク日系人会の会長をつとめたのちに、終身顧問になっている。
その江見家の子息はハーバード大学に入り哲学を研究していたが、「哲学などやめてほしい。頼むから医者になってくれ」と親から説得され、世界一周旅行をプレゼントするからと言われて、わざわざマサチューセッツ大学の医学部に転学したという。この江見家の考えは、医療界の家系ならばよくわかるのではないだろうか。
私が清木氏の話を聞いた時には、江見順子氏はすでに医院を閉じ家族ともにブルックリンのパーク・スロープに移住してリタイヤメント・ライフを楽しんでいるとのことだった。しかし三年前の二〇一七年、私がもたもたしているうちに他界してしまった。
この江見氏だけに焦点を当てても、うまい作家ならば、いい本を書くのではないかとも思われた。
たしかに私の親類にも、開業医に嫁いだ薬剤師や大学教授になった者、東大を出て弁護士になったり医師になった者がおり、いまだに私の祖父(故人)にも相応の親しみはあるから、そういう明治、大正、昭和を生き抜いた長老を祭るのは、どこにでもある昔ながらの「しきたり」かもしれない。
しかしこの清木美徳氏にはまだ何か、稀有なものがあるのではないかと思っていた。それが、八十歳を超えて日本史に向かわせたのではかったか。
ヒントは、清木氏の親族の遺した自費出版物のなかにあった。
そのなかには、やはり「南無地獄大菩薩」が登場する。
書いたのは、清木氏の娘の夫、開業医(故人)のA氏だった。
A氏はその本にこう記している。
「地獄に落ちたような困難苦労が、かえって将来の自分自身のプラスになる、つまり幸福の元になるから、決して困難にめげることなくがんばりなさい、という意味です。この南無地獄大菩薩と言う言葉は、我が家の家訓として、岳父清木美徳様から引き継いでいるお言葉でもあります。教えでもあります」とある。
高校受験に失敗したこと、自分はどのような問題を解いて受験に成功し、いかに苦労して大学に入り開業医になったかなどが丹念に書かれている。孫たちに向けて書いたのだろうか。
そのほとんどは医師になるまでの学業に対しての処世術なのだった。
しかしそれは「苦労は買ってでもしろ」ということではないこともわかる。
A氏の記述で興味深いのは、「友人から進駐軍の家族の家具を運び込むアルバイトをしないか」と誘われたときの話である。
タコ部屋での労働環境の悪さ、想像を絶する待遇、ひどい仕打ち、給料も満足に払われなかったこと。これらが淡々と書き綴られたうえで、喜寿(七十七歳)をすぎたというA氏は、子孫に向けて次のように書く。
「しずかに、私のこのアルバイトのもたらした結果について、喜寿を過ぎた今、振り返ってみますと、私のその後の人生を変えてしまうほどの、大きな悪い影響を及ぼしていることに気づきます。このアルバイトによって失ったものの大きなひとつは、毎日こつこつと勉強を楽しんでいく、という習慣を中断したことです。勉強はこれを習慣化し、慣性をつけることが大切です。心理学的研究によれば、学問を始めていくと数々の困難な問題に直面しますが、その困難を乗り切っていくうちに、学問に対して興味が出て来て、毎日の勉強が次第に慣性がつき、ますます勉強が面白くなっていく、という心理があるのです。もうこうなってくればしめたものです。反対に、もしこれを私のようにアルバイトなどで中断すれば、またこの勉強の慣性を取り戻すためには、また始めから莫大な努力をし直して追いつかねばなりません。学問は、ドイツ語であれ、数学であれ、物理学であれ、あたかも螺旋階段を上るように、基礎からこつこつと上っていかねばならないのです。ですから「孟母断機の教え」のように、中断のための遅れを取り戻すには、私は、大変な努力を要したのです。私は必死の努力はしましたが、ついにドイツ語には十分の自信を持つには至りませんでした。それで仕方なく、ドイツ語を含む二ヶ国語の試験科目のある大学は敬遠しました。たとえば、友人が勧めた東大医学部、京大医学部などです」(※友人の氏名は、筆者が割愛してある)
開業医のA氏は、このように書き、戦争はしてはならないこと、健康が大切であることに加えて、「青年期には決してアルバイトをしないことが大事です」と書き遺すのだった。
彼女は思い出したように言う。
「私の家もアルバイトは禁止だった。たぶん祖父の考えと思う。それだけでなく、私の母親は、祖父から文学作品や新聞なども読ませてもらえなかったと聞いたことがある。思想にかぶれて勉強しなくなり、あるいは学生運動などに走ることを怖れたのかもしれない」
孫である彼女自身が、この清木美徳氏を痕跡を尋ねる旅に出る。それは自分のルーツを探る旅でもある。なぜ、清木氏は、八十歳にもなって「日本史の勉強をはじめたのか」。これを、彼女自身が追っていく本が面白いのではないかと、当初は考えた。
グランド・ゼロといえば爆心地のことをいう。広島や長崎、スリーマイル島の爆心地を言っていたが、二〇〇一年九月十一日に、アメリカ同時多発テロ事件、いわゆる911が起こってからは、倒壊した旧ワールド・トレード・センターがそう呼ばれるようになってしまった。ならばタイトルは「もう一つのグランド・ゼロ」にしよう。
そんな話しているうちに自分が書きたくなり「それ、書かせてよ」となったわけである。
実は私には、妙な推測もあった。
清木氏は、物理学者としての純粋な科学への関心と被爆者としての体験のなかで生涯揺れていたのではないかということである。科学者として生きた八十歳までと、政治や歴史に関心を持つ学者としての残りの十五年は、まったく違う研究のアプローチ、考え方をしたのかもしれない。
日本の原子爆弾への研究は、すでに広島や長崎に原爆が落とされる五年も前の一九四〇年に始まっている。このあたりはすでに資料も数多くある。
理研の仁科芳雄氏と東京帝国大学理学部化学科の木村健二郎氏による論文には、ウラン238に高速中性子を照射した実験において核兵器の爆発によって生成することや、ネプツニウム237を生成したことが記され、同年、米国の物理学誌フィジカル・レビューに掲載されている。
また原爆投下の一年前、一九四四年三月の日本の新聞記事には、「ウラニウムから特殊原子量のものを抽出し、これに宇宙線をあてることにより非常なエネルギーを出すということをある学者が成功した。マッチ箱ひとつのウラニウムでロンドン市全体を潰滅させることができる」といった記述がある、一九四四年の四月の新聞にも「特集決勝の新兵器」という形で原爆が紹介されているから、のちの理学博士である清木氏が、物理学者として関心を持たないはずもない。
そして前述の、永井氏もまた科学者として、この未知なる兵器に関心を持っていた。それは、核兵器を憎むというものとは別の、科学者としてのベクトルを持っていた。
これらが実現していれば日本はアメリカに原爆を落とすことができ戦勝国となったかもしれないといえば語弊があるだろうか。しかし原爆投下時は、まだ戦中なのである。
そういった混乱は、永井氏の書いた『長崎の鐘』の次の文章を見てもよくわかる。
少し長いが引用しておこう。
『長崎の鐘』より
原子内で帯電粒子の急激な位置移動が起こる結果として電場磁場の歪みを生じ、これが電磁波として輻射される。それを波長の短いものから並べてみれば、ガンマ線、エックス線、菫(きん)外線、光線、赤外線であろう。さらに波長の長い電波も出るかもしれぬ。その速度はいずれも一秒間に二十九万九千七百九十キロという素晴らしいものである。光線がピカッと眼を射たあの時刻が原子爆裂の時刻であり、同時に恐ろしいガンマ線は身体を貫いており、赤外線は露出部に熱傷をあたえたのである。
清木先生を中心に長老たちがしきりに論じている。
「一体全体これを完成したのは誰だろう? コンプトンだろうか、ローレンスだろうか?」
「アインシュタインも大きな役割を持っているにちがいない。それからボーアやフェルミなど、欧州から米国へ追われた学者たち」
「中性子を発見した英国のチャドイックや、仏国のジョリオ・キュリー夫妻や」
「もう何年も学術鎖国で重要な文献が発表されないからわからないが、きっと新進大家がいるにちがいない。そしておそらくは米国のことだから、数千人の科学者を動員し、研究の分担を定め、能率的にどしどし仕事を進めていったものだ」
「こりゃ実験室だけの仕事じゃないから、材料の採掘、精錬、分析、純粋分離というだけでも大した工業力が要るんだぜ。きっとあとで発表になってみれば、日本の兵器研究所なんて向こうの規模に比べたら、まるで丸ビルの横丁に落ちているマッチ箱みたいなものだろう。多分何十万という労働者の力がこの一発の原子爆弾にこもっているよ。何十人か何百人かの女学生がこっそり紙と糊とで造った日本の秘密兵器とは桁が違うよ」
「材料といえば、一体何原子だろう? やっぱりウラニウムか」
「さあ、もしかしたらアルミニウムのような軽い原子じゃなかろうか」
「でもそんな小さな原子じゃ、解放される力も小さいだろう」
「しかし、ウラニウム原鉱は地上に少ないよ。これだけの大戦争に使用するためには、容易に手に入る元素がないと思う」
「なあに、ウラン鉱はカナダからいくらでも出るんだ」
「材料と関係のある話なんだが、一体どういう方法で、希望の瞬間に、大量一時に、原子爆裂を起こさしたものだろう」
「さあ、それだ。それが各国物理学者の知恵比べの焦点だったんだ。さっき、ローレンスの名が出たね、例のサイクロトロンで原子核破壊の第一人者だが」
「まさかあの爆弾の中にサイクロトロンを入れることはできまい。理化学研究所のを見てきたことがあるが、大きな建物一つほどのでっかいものだぜ」
「それをなんとか小型にしてさ」
「いや、高圧絶縁とか電磁石とかを考えれば、ちょっと小さくはされないね」
「ラジウムかなにかを使って、アルファ線のようなものを利用したら?」
「それとも宇宙線の中間子なんか利用できんか」
「あっ、思い出した。そうだ、フィッションだ」
「なんだ、なんだ。フィッションとは?」
「フィッションだ。核分割だ。マイトナー女史が見つけた、あの現象だ」
「マイトナー女史、あまり聞いたことのない名だなあ、どこ人だ?」
「オーストリア人だ。研究したのはコペンハーゲンでだ。やっぱりヒトラーから追われた学者の一人だ。ハン博士の助手だったが、今は六十歳をよほど越したお婆さんのはずだ。伊国のフェルミ教授の仕事に関連しているのだがね。ウラニウムの原子核に遅く飛ぶ中性子を当てると、ウラニウム原子がぽっかり二つに割れるのを見いだしたんだ。あまり速い中性子だと、原子核を単に貫通してしまってなんにもならないのだ。のっそり飛んできた中性子が原子核の中へもぐり込むと、もごもごしていて、突然核が二つに割れて離れる。そして核内に潜在していた巨大な原子力が解放されて噴出する」
「ほう。便利だねえ、中性子がありさえすりゃいいじゃないか」
「この時おもしろいことは、二つに割れた部分の質量が元の質量より減っているという事実なんだ。これはもう以前にアインシュタインが発表したエネルギーと質量の同等性という理論を事実において証明したもので、物理学の革命とも称すべき、科学界における最近の最も重大な開拓であったわけなんだね。つまり、核が二つに割れる際にその一部の質量が、いいかえれば物質が忽然として消滅し、それと同時に一定の同等量のエネルギーが発生するのだ。つまり原子爆弾のエネルギーがそれなんだ」
「物質がエネルギーに忽然として変わるんだ」
「そうだ。物質の質量に光の速度の自乗を乗じた積が、その質量のエネルギーなんだ」
「光の速度が約三百億毎秒センチだから、その自乗とは素晴らしく大きい数だが、一グラムの質量がエネルギーに変わるとすると、一体どのくらいになるだろう」
「まあ概略の計算をすれば、一グラムの物質がエネルギーに変わると、一万トンの物を百万キロ運ぶだけの力となるね」
「うへえ!」
「この浦上を潰した原子爆弾にしたところで、そりゃ原子もかなり大量に使ったろうし、いろいろな器械で、弾体は魚雷くらいの大きさはあったかもしれないが、正真正味消費せられた原子の質量は、おそらくは何グラムという小さいものだろう」
「すごいな。だがたくさんの原子核を一時に分割するには中性子をどうして発射する?」
「それがまた都合のいいことには、ウラニウム原子核がフィッションを起こすと、ガンマ線も出るが、大体二個の中性子も飛び出すのだ。そしてこの二個の中性子が、近くの核にぶつかってさらに二個所でフィッションを起こす。それから二個ずつ中性子が出て今度は四個の核を割る。次は八個、十六個、三十二個、六十四個」
「百二十八個、二百五十六個、五百十二個、千二十四個、二千四十八個」
「こうして最初は少し割れるが、短い時間後におびただしい数の原子が同時に爆裂する。これを連鎖作用というんだ」
「それじゃ、まず最初に少なくとも一個の核を割れば、あとはひとりでにそこにあるだけの原子が割れるわけだね。しかし厳密な意味では同時でなく、ある時間を要するわけだ」
「そういえば、爆圧の来たのが、一瞬間ではなくて、幾秒間か続いたようだった。最初少し弱いのが来て、急に強くなったと覚えている。その後に続いたのは反射干渉の結果の圧力だったろうけれども」
「日本ではこんなことを知らなかったのかい?」
「知ってたさ、僕だってこうして知ってるんだもの」
「じゃ、なぜやらなかったんだい?」
「マイトナーのこの実験は戦争の始まるよりずっと前なんだ。だからどこの国もやりかけたんだが、フィッションを起こすのはウラニウムで、そのウラニウムには同位元素のウラニウム235と238とがあるが、235のほうがよく割れるんだね。もしウラニウムの中に他の元素が混入していると、それは割れないから、中性子が飛んできても、もうそこで連鎖作用は中断されてしまう。したがって、連鎖作用を完遂するためには純粋ウラニウム235だけの集まりを得なければならない。これがなかなか難事業だ。日本ではこのウラニウム235の純粋分離をやりかけたのだが、軍部から、そんな夢物語みたいな研究に莫大な費用を使ってもらっては困ると叱られて、おじゃんになったともれ聞いている」
「惜しかったなあ」
「すんだことは仕方がないさ。愚者を指導者にいただいた賢者の嘆きさ。それからね、核が分割して中性子が出るのだが、ウラニウムの塊があまり小さいと、外へ、すなわち空気中へ飛び出しちまって、これまた連鎖作用の終末となる。だから、ウラニウムの塊は十分大きくなければならない」
「純粋のウラニウム235を十分大量に得るというのは、容易な工業じゃないぞ。米国は持てる国とはいえ、随分苦労したろうなあ」
「米国の科学陣の勉強ぶりも想像されるが、また、これは放射能物質をあつかう仕事だから、たくさんの犠牲者が出ているにちがいない」
「犠牲者なくして科学の進歩はないさ」
「僕はウラニウムと思うけれどね、また新しい人工原子かもしれんとも考えられる。この方面の第一人者、ローマのフェルミが米国へ渡っているという話だから」
「とにかく偉大な発明だねえ、この原子爆弾は――」
かねて原子物理学に興味をもち、その一部面の研究に従っていた私たち数名の教室員が、今ここにその原子物理学の学理の結晶たる原子爆弾の被害者となって防空壕の中に倒れておるということ、身をもってその実験台上に乗せられて親しくその状態を観測し得たということ、そして今後の変化を観察し続けるということは、まことに稀有のことでなければならぬ。私たちはやられたという悲嘆、憤慨、無念の胸の底から、新たなる真理探求の本能が胎動を始めたのを覚えた。
勃然として新鮮なる興味が荒涼たる原子野に湧き上がる。
※「長崎の鐘」日比谷出版、一九四九年一月三十日発行
原爆の被害に遭った直後に、原子物理学の研究と被害とを語るこういった思考。これには違和感を覚える人もいるかもしれない。しかしそこが、私の好奇心をくすぐるのである。
昭和五年生まれの開業医が、原爆をどう感じてきたか。それもまた面白い。
八十歳を超えて、日本史の勉強を初めたという私の知り合い女性の祖父の清木美徳氏と、その家訓である「南無地獄大菩薩」を通じて、色褪せつつある昭和の激動を描けないだろうか。そう思いつつ十九年の歳月が流れ、私はそれを断念した。
二〇二〇年の六月十二日、西日本新聞は「戦跡をたどる 現地からの報告」として、医学部の前身、旧長崎医科大の付属機関・薬学専門部の教授と学生が掘ったこの「薬専防空壕跡」の写真と「助かったのは、壕の中で作業をしていた清木教授と5人の学生だけでした」との客員教授の三根真理子さん(七十)の言葉を伝えた。
「二〇一八年五月、壕の説明板が設けられた。自分のためだけではなく、誰かのために 壕を掘り、水を飲ませた。そんな尊い行為があった場所なのだ」とその記事は結んでいた。
私はまた、孫娘の彼女に聞いてみる。あなたの祖父に何があったのか。
「日本史を学ばないと解決しない、何かがあったのでしょう」
彼女は、何を今さらという顔をして、さらりとそう答えた。
(了)

・『PCR検査を巡る攻防』の1話を試し読みする(ここ)